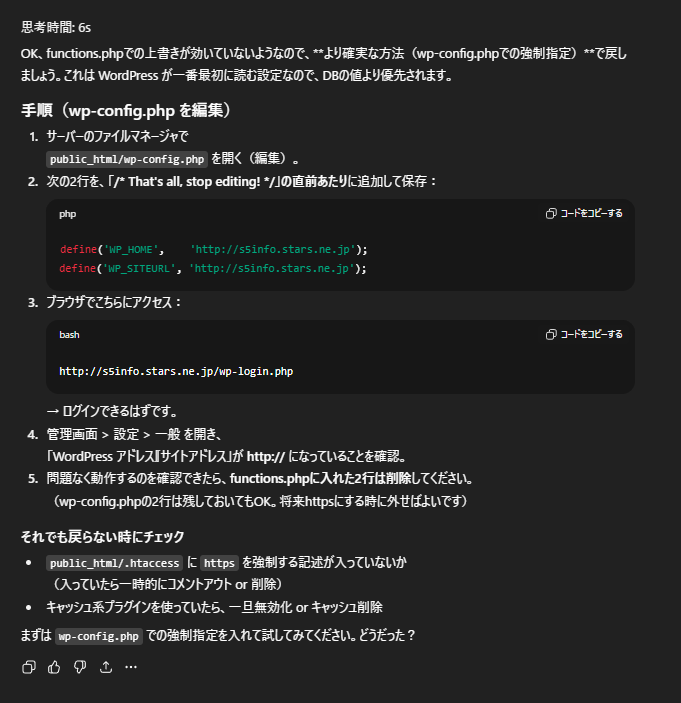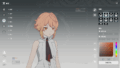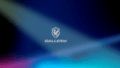2か月くらい前からChatGPTで遊んでいることが多い。昨今のWebサイトはSEO対策だけ無駄に施したサイトが多いため、ブラウジングして情報を集めるよりAIに質問したほうが中身のある回答が返ってくると感じる場面が多々ある。
そこで今回はChatGPTの仕様を調査したのでまとめてみた。有料版を2か月使用する中で疑問に思った仕様をGPT側に何度も質問し、精査を行った。
基本知識
・プロジェクト=チャット
(技術的には別物だけど、ユーザー目線では同一視してOK)
・内部的にはプロジェクトの中に「チャット」「キャンバス(文書やコード)」が複数入るイメージ
※キャンバスの正式名称はTextdoc。
・キャンバスは長文のドキュメント編集に向いている。
プロジェクト単位
・各プロジェクトは「別のフォルダ」みたいな扱い。
・そのプロジェクト内では、過去のやり取り(履歴)がそのまま見える。よって同プロジェクト内なら「昨日の続きを話そう。○○について」等のチャットを入力すれば、前提の説明なしに続けられる。
別のプロジェクトでも同じ話をしたい場合
・他のプロジェクトの中身は基本的にGPT側では把握できない。
・ただし「最近使ったチャットの一部(数件分)」はGPT側で参照できることがある。
→これはセッション単位のキャッシュ的なもので、必ず参照できるわけではない。
・「短期の橋渡しは運次第、長期の橋渡しはユーザーがやる必要がある」
→ユーザー側がテキストファイル等で会話内容を管理する必要がある。
会話の引き継ぎ
・長期的に別プロジェクトへ内容を持ち越したい場合、テキストファイルなどに会話内容をまとめた「橋渡しテキスト」や要約を自分で渡す必要あり。
・橋渡しをしないと新しいプロジェクトでは空白からのスタートになる。
常に把握しておいて欲しい記憶(ユーザー情報)
・「記憶」は全プロジェクト共通の長期ストレージ。
・「会話ログ」は各プロジェクトごとの短期履歴。
・「趣味はカレー作り」のようにユーザーの情報としてGPT側に把握しておいて欲しい情報は「記憶」で残すのが確実。
チャット例:「記憶して:私の趣味はカレー作りです」のように文章をあらかじめ入力しておく必要がある。
記憶の容量
・GPT側の記憶容量には上限がある。
・新しく記憶すると古い記憶が削除されることもある。
・管理画面から手動で「不要な記憶を消して容量を空ける」ことができる。
◆補足
記憶の削除(容量削減)は「設定」>「パーソナライズ」>「メモリを管理する」からユーザー側で整理する。
安全設計
・GPT側が他プロジェクトの中身を丸ごと勝手に参照することはない。
・あくまで「最近の数件を便宜的に拾えるだけ」であって、プライバシーや分離性を守るための設計になっている。